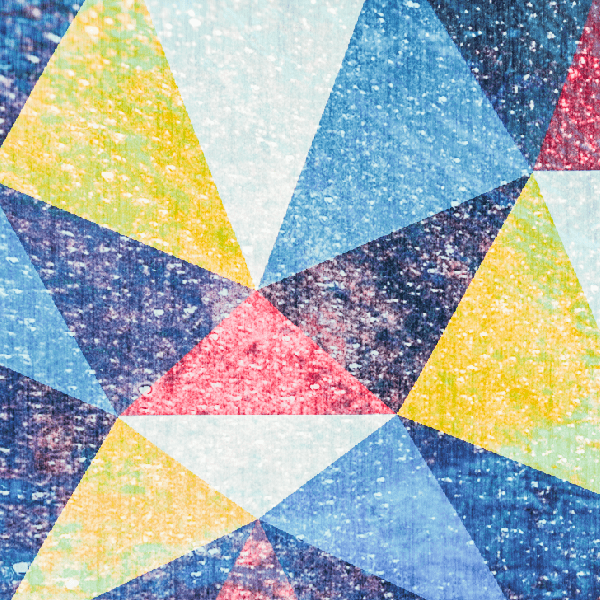
嫌いになりたい①
アラームの音で目が覚めた。
「寝ちゃってた……」
朝の8時。休みの日は、いつもこのくらいに起きてる。
ダンデの帰りを待つつもりだったのに。眠気には勝てなかったようだ。……結構図太いな、私。昨日あんなことがあったのに。
「そうだ、ダンデ」
ダンデ、がっかりしてないかな。帰ってきたら私が先に寝てて肩透かしを食らったに違いない。だってダンデ、私の頬にキスしたくらいだし。こう、色々私と話すことを期待してたんじゃないな、と思う。
「……手紙のこと話さなきゃ」
帰る手段が分かったって教えなければ。ジラーチの短冊で帰れるかもしれないって。
おばあちゃんの手紙と短冊は、寝室の箪笥に仕舞ってある。念のため確認したら、しっかりあった。夢じゃなかった。
正直、これは話したくない。ダンデに帰ってほしくない。また私は、独りになる。家族のいない寂しさに押し潰されてしまいそうになる。
ずっと傍にいてほしい。
でも、今はともかくダンデに挨拶。あと、先に寝ちゃってごめんって謝ろう。
私は意を決して寝室のドアを開けた。
「おはようダンデ! 先に寝ちゃってごめ、」
「おはよう!! !!」
「まぶしっ!?」
ま、眩しい! 眩しい!!
目が焼けるどころの騒ぎではない。なんだあのキラキラした生命体は!? 太陽の擬人化か? いや太陽神か?
ジムリーダーやチャンピオンの夏のカレンダーが作られるとしたら、ダンデは8月に採用されるだろう。そのくらいのキラキラ笑顔と爽やかさ。
おまけに「キミが愛しい」と瞳が訴えてくる。ダンデファンの皆様、ご覧下さい。あれが恋するガラルのチャンピオンです! 熱量がすごい!
「いいんだ。オレも結構長いことリザードンに乗っていたから。帰ってきたのは深夜2時くらいだ。先に寝ていて当然なんだぜ」
「そーだったんだ」
ダンデはいつものエプロンとポニテスタイルだった。いつの間にか私に近付いてきていて、そっと私の手を取った。
「ん、ダンデ?」
「おはよう」
何でもう一回挨拶?
「? お、おはようダンデ」
すると、ダンデが私の手の甲に口づけた!
「!?」
紳士の挨拶か何か? ドラマでしか見たことない!
「、照れてるんだな」
「うぅあ……」
「昨日は夢じゃなかったんだな。……よかった」
そう、夢じゃない。
私たちは両想いだ。
「うん。夢じゃないんだよね……」
ダンデのことは大好きだ。
家族になってほしい。
だけど、それは難しい話だ。
「朝食、食べるだろ。準備できてるぜ」
「食べる! あと、朝食のあと話したいことがあるんだけど」
「ああ。オレも!」
――恐らく私は、ダンデのその幸せそうな顔を曇らせることになる。
そう思うと憂鬱だ。
***
「改めて言うが、オレはキミが好きだ」
ご飯食べ終わってひと息ついたらこれだ。
今日はリザードンがボールから出ていて、じっと私たちの様子を見守っている。多分、ダンデが昨日のように暴走しないか目を光らせているのだろう。だって、ダンデを見る目が厳しいから。本当に賢くていい子だよね、この子。
「その……、めんどくさいこと訊いても?」
「めんどくさいこと?」
「うん。私のどの辺りを好きになったのかなと」
「理由が知りたいのか」
私はうなずいた。
「理由か。挙げればキリがないぜ?」
「そんなにあるの?」
それから、ダンデが1個1個「の好きなところ」を話してくれたが、それは私の羞恥心を煽るだけだった。
おかしいな。私はそんな、大層な女ではないのだが。
「あとは、これだな。嬉しかったんだ。『チャンピオンのダンデ』じゃなくて『ただのダンデ』を知りたいと言ってくれたことが」
幼い頃からチャンピオンとしてその座に居続けたダンデは、いつの間にか、チャンピオンとしての振る舞いが当たり前になっていた。
「前にも言っただろう、『ただのダンデ』がどんなだったかを忘れていたと。キミがきっかけなんだ。キミが隣にいてくれたら、オレはきっと、もうオレを見失わない。そう思うんだ!」
つまり、とダンデは言葉を続ける。
「……キミはオレの居場所なんだ」
居場所。
「オレがオレでいられる。ありのままでいられる場所だ」
ああ、
「オレの恋人になってくれないか」
でも、それは――
「無理だよ、ダンデ」
私もダンデの恋人になりたい。
「ダンデのことは大好き。でもね、世界が違うんだよ」
ダンデの家族になりたい。
「私たちは結ばれない」
傍にいてほしい。
「ダンデの恋人には、なれない」
世界で一番残酷な言葉を、私はダンデに突きつけるしかなかった。
「……」
嫌な沈黙だった。
ダンデは目を伏せて動かない。
ダンデの後ろにいるリザードンさえ身動ぎしない。尻尾の炎が、ゆらゆら小さく揺れるだけ。
いたたまれなくなって、私はダンデから目を逸らした。
「――イヤだぜ!」
えっ、と私はダンデを見つめる。
「イヤだぜ! オレは、キミを諦めない!!」
ぐっとダンデが拳を握る。
「世界が違う? それがどうした!」
カッと目を見開いて、ダンデは立ち上がる。
「それは、キミを諦める理由にはならない! 見つけよう。帰る方法も、キミと一緒にいられる方法も!」
そして、私の手を、その大きな手で包み込んだ。
「だから、オレの隣に居てくれ」
ああ、どうしよう。
帰る方法はもう見つかってるのに。
ダンデに必要とされているのが嬉しくて、離れたくなくて、――言い出せない。
どうしよう。どうしよう。どうしよう。どうしよう!
「ダ、ダンデ……、あの」
包まれた手とダンデを交互に見やる。
ダンデと一緒にいたい。
でも、ダンデは帰らないといけない。
「つまりその、一旦帰ってまたこっちに戻ってくる方法を考えてるとか、そういう……?」
「ああ!」
ちょっと待って。
「もしくは、がこっちに来ればいいじゃないか」
「――」
私が、あっちの世界に?
「。こっちの世界で言う、鳩が豆鉄砲食らった顔してるぜ」
「仕方ないじゃん! そんな簡単にサラッと大変なこと言っちゃうんだもの!」
そりゃ、あっちの世界に行けたら……いいけど……。
私だって生活があるわけで。いきなりあっちの世界に飛び込むのはちょっと……いや、かなり怖い。
「無理でしょ。帰る方法も見つかってないのに」
嘘をついてしまった。胸が痛む。
帰る方法がなければダンデはずっと私と一緒だ。そう考えてしまって……短冊のことを言い出せない。
「無理じゃない。最初から決めつけたら何もできない。諦めるのは、全てを探し尽くしてから。それからだ!」
「……うん」
どうしよう。言わなきゃ。帰る方法があるって。
なのに、言い出せない。
「とにかく、帰る方法を見つけようぜ! それが、世界を渡る方法に繋がるはずだ!」
ごめん、ダンデ。
ごめん、あっちの世界の人たち。
もう少しだけ、ダンデの傍にいさせてください。
***
「……あ。それはそれとして、ダンデの恋人にはなれないからね」
「えっ」
今度はダンデが「鳩が豆鉄砲を食らった顔」をする番だった。
「どうしてだ、!?」
「万が一方法が見つからなかったら……、別れるってことでしょ。イヤだよ私。そんなの耐えられそうにない!」
短期間で2回も別れを経験したくない。
「それに、私は家族が欲しいの! 重いかもしれないけど、結婚を前提にお付き合いがしたいの!」
つまり、
「夫になる覚悟がなきゃダメです!」
「なるほど……?」
「うん。だから、恋人云々は保留で……」
ダンデはがっくり肩を降ろしていたが、
「そうだよな、は前からそう言っていたな」
と呟いて、
「世界が違う問題が解決すれば、キミは首を縦に振ってくれるんだな?」
「そういうことになる、ね?」
「――分かった。キミと家族になりたいから、オレは頑張る! だから、あとは世界を超える問題だけだぜ!」
私は卒倒しそうになった。
ダンデ、そこまでしてくれるの?
私と家族になってくれるの……?
3ヶ月かそこらの出会いの私のために……?
どうしよう! やっぱり離れたくない!
ますます短冊のことを言い出せなくなってしまった。