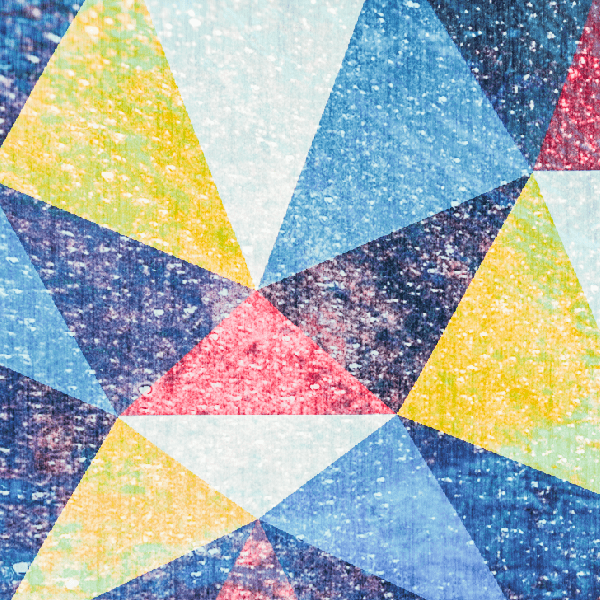
あなたと暮らすためのアレコレ③
チャンピオン、と讃える声がする。
ただ、楽しかったんだ。
ポケモンと暮らすことが。
ポケモンと一緒に旅をすることが。
ポケモンとバトルをすることが。
楽しかったんだ。
楽しいが積み重なって。
オレの身体を、心を、熱くする。
自分の「楽しい」を分かち合いたくて。
勝って、勝って、勝って、勝って……。
いつの間にか、オレはその頂に手を伸ばしていた。
今もずっと、そこに座している。
誰かを待っている。
何かを待っている。
オレの願いは、ガラル地方のポケモントレーナー、皆で強くなること。
待っている。
待っている。
チャンピオンは、待っている。
いつの間にか与えられたそれを乗せて。
オレは、チャンピオンは、チャンピオンとして――。
寒さで目が覚めた。
いつの間にか眠っていたらしい。疲れていたんだな。ソファから身を起こす。
目を覚ましたら何もか元通りになっていることを期待していたが、まあ、そんな上手い話はないか。
「日が暮れているな。そろそろ、彼女は帰ってくるだろうか」
時刻を確認し、カーテンを閉め部屋の電気を点けた。玄関の鍵は開けておいてやる。
そういえば、腹が減っている。……リザードンもそうだろう。この家の主が帰ってくるまで、オレは何も出来ない。チャンピオンなのに、今は何も出来ない無力な大人だ。
頼みの綱は、彼女だけ。
情けない。いや、弱気になるな、オレ。すぐさま気持ちを切り替える。
玄関の方から音がした。人の気配がする。彼女だろうか。
話をしなければ。オレの今置かれている現状を確認するんだ。冷静に。
こうしてオレは、彼女と二度目の邂逅を果たした。
驚くべきことに、彼女は今朝より冷静にオレの話を聞いてくれた。何があったのかは分からないが、これはチャンスだと思った。
お互いに今朝のことを謝って握手をする。小さな手だった。守るべき、子どもの手だった。やはり彼女は小さくて幼い少女だ。
子どもに頼らなければならないことに、オレは罪悪感を覚えたのだった。
***
暖められた部屋で、オレは食事を貰った。おにぎりというらしい。ガラルにもあったとは思うが、名称が違うし、何よりガラルでの主食はパンだ。カレーの時くらいだろう、米を口にするのは。
胃が食べ物を欲して限界を迎えていたので、オレは遠慮なくおにぎりを頬張った。
彼女の作ったおにぎりは美味しかった。中に入った具はペラペラとした、茶色のセロハンのようなもので、本当にこれは食べ物なのかと驚いた。これは何かと聞いたら「おかか」と彼女から返ってきた。耳慣れない単語だ。「魚の……干した奴? お醤油染みて美味しいと思う」と説明される。
食べてみれば、今まで味わったことのない旨味が口いっぱいに広がった。なるほど、美味い。この独特なコップに入ったお茶も美味い。コーヒーと違った渋みがあって、このおにぎりに合う。
玉子焼きも美味かった。どれも片手で食べられる。手早く食べられるのもポイントが高い。
オレが夢中になって食べている間、彼女は驚くべきことを口にした。
オレにとって、ここは異世界だということ。
この世界にはポケモンは実在しないこと。
ポケモンはこの世界ではゲームであり、世界規模で人気があるということ。
ちょうどこの時期、ポケモンの新作が発売されて、その物語はガラル地方であること。
――ここは、違う世界なのか。
腑に落ちるものがあった。
読めない文字、見慣れない生き物、知らない街並み。……むしろ、そうでなければ説明がつかないことばかりだ。
オレも彼女へここに来た経緯を話す。ムゲンダイナをゲットした直後、気を失ったこと。十中八九、ポケモン絡みでこちらの世界へ来てしまったのだろうということを。
「一刻も早く帰らないと……」
そう、家族がいる。ガラルの皆がいる。無事を伝えたい。
ローズ委員長が引き起こそうとしたブラックナイトは収束。オレの怪我も大したことはなくて、保留になった決勝戦も再開出来ると。
皆が待っているんだ。
気持ちが逸るが、そこでもう一人のオレがストップをかける。
帰り方も分からないのに焦ってどうする。
まずは、これからの暮らしを考えろ。
そうだ、これからどうするかだ。
帰り道を探す間、オレは恐らくこの世界で生きていかなければならない。
右も左も分からない。彼女にこれ以上頼るのは情けないが、ここは助けを求めるしかない。
彼女といえば、少々気難しい顔をしてオレをじっくり眺めていた。
……図々しいよな。
いや、オレは元の世界へ帰るんだ。そのためにも、彼女に協力を仰ぎたい。
だから、彼女が「ここに住みましょう」と提案してくれたのは、ありがたいことだった。
逆が何だとかよく分からないことを言っていたが、まあとにかく、当面の宿は確保出来たんだ。感極まって思わずまた握手をしてしまった。
しかし、今朝あんなに取り乱していた彼女が、こうしてオレに親切にしてくれるとは……。
異世界から来た物珍しさもあるのかもしれないが、親切な人間に出会えてオレはラッキーだったな。
そうだ。彼女の名前を教えてもらった。。いい名前だ。
共に暮らすからには、情けないところは見せられないな。
衣服やリザードンの食事まで助けてもらってしまったが……。どのくらいかかったのか、後で訊いておこう。返しておきたいからな!
「あー、良かった。服のサイズいい感じで……。じゃ、リザードンのために外へ行きましょう、か……」
「? どうしたんだ?」
公園に行こうとして、くんは身体を硬直させた。視線を辿る。オレの足元を凝視していた。
「靴がどうかしたのか」
「あっ……、あっ……。ダンデさん、あのね。日本はね、室内は土足厳禁なんです……」
「うん?」
どういう意味なんだ?
「家に入るときはね、この玄関で靴を脱いで、スリッパに履き替えて部屋に上がってください……」
「…………」
オレは彼女の足元を見る。スリッパを履いていた。
廊下はオレの足跡で汚れていた。オレは片手で顔を覆った。
「それは、すまなかった。知らなかったんだ……」
「いやいや、いいんです。異文化コミュニケーションだから……。教えなかった私が悪いから……」
シキキン、とくんは悲しい声で呟いていた。本当にすまない。
***
公園でリザードンを出した。見たところリザードンに異常はなく、与えられた果物も素直に喜んで食べていた。
くんは初めて見るリザードンに少し怖がっているようだったが、ふれあいを経てその恐怖を取り除けたと思う。
帰り道、彼女とこんな話をした。
「キミは、一人暮らしなんだよな」
「そうですよ」
そうでなければ一緒に住もうって言いませんよ、と彼女は小さく笑う。
まだ幼いのに、とオレは暗い気持ちになる。オレが彼女くらいのときは、チャンピオンとしてインタビューを受けたり、スポンサーへ挨拶回りをしたり、バトル以外のことをたくさん覚えなければいけなかった。
慣れないことに目を回しかけていたが、オレにはそれらを乗り越えられるくらいの胆力と要領があった。
それは、普通ではないのだと周りの大人から言われた。立派なことです。キミは非凡です。稀有な人間です。チャンピオンになるべくなったのです。そう、褒められた記憶がある。
この世界は、幼い子どもでも会社勤めをするようだ。ポケモンもいないのに、よくやっている。
居候の身だが、彼女を守ろう。
鍵のかけ忘れの件もあるし、オレがしっかり見ておこう。
「ダンデさん、どうしました?」
「キミは偉いぜ!」
「え? いきなり何を?」
「共に暮らすんだ。これからは遠慮なくオレに頼ってくれ」
「は、はあ……? よろしくお願いします?」
「ああ、よろしく」
くんは困惑していた。その顔が面白くて、オレは微笑んだ。
並んで歩いたその日の夜。
満天の星が、輝いていた。