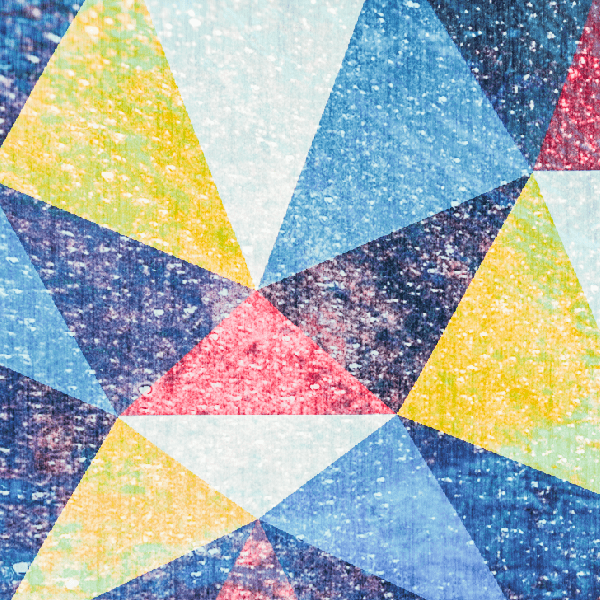
これはデートだから、②
***
それから私たちは、ダンデ帰還の準備を始めた。
まずはズシに、帰る方法が見つかったことを電話で打ち明けた。
私のおじいちゃんのこと、ジラーチのこと、短冊のこと。それから――私のわがままで、これらのことを今まで黙っていたことを。
ズシは私が話し終わるまで無言だった。その後、「分かった。仕事終わったらちょっと寄らせて」と言い、夜に家にやって来たのだけど……。
「ねえ、何でプラスチックの野球バット持ってきたの? 買ったの? わざわざ?」
「買ったわよ、わざわざ。に好きって言っておきながら置いていくこの男のケツを叩かないと気が済まない」
ズシが力強い素振りを見せる。ブォン、ブォンと空気を切り裂く音が聞こえた。この勢いでケツバットされたら、お尻の感覚なくなりそうだわ。
「もー! だからのことを思うなら深入りすんなって言ったじゃん! 結局を置いていくんだからさあ! おら、チャンピオン! ケツバットの餌食になれや! これは罰なんだからね! 削ぐよりいいでしょ。譲歩してんだからね、これでも」
「くっ……。そうだな、返す言葉もない。ズシの言う通りだ。それでキミの気が晴れるなら遠慮なくオレの尻を叩くといい」
言うなり、ダンデはテーブルに手をついてお尻をこちらに突き出す。形のいいお尻ですね。……じゃなくて!
「ええ!? ダンデ、受け入れるの? 絶対痛いって。ズシは加減してくれないよ」
「聞き分けよすぎよね。これじゃ罰にならないじゃない。まあ、やるんだけど。はいズバァン!」
「い"っ!!」
「わああダンデー!?」
容赦のない一撃だった。ダンデの背中は弓なりにしなり、床に崩れ落ちた。
私は、お尻を押さえて小刻みに震えているダンデに駆け寄った。
「大丈夫?」
「っ、……わ、割れたかもしれない」
「安心しなさい。元からケツは割れてるわよ」
「それはそうだけどさあ……」
「あ、あと。。おでこ出しな」
「え」
まさかの一言に私は一瞬固まった。
「何するの」
「デコピン。いくらダンデと離れたくなかったとはいえ、帰る方法を黙ってたのはダメでしょ。あんたにも罰が必要よ。ほら」
「……うん」
ズシの言う通りだ。私はダンデの前髪をあげて、ズシからのデコピンを受けた。
「いっ! ――ったくない……」
「ま。今度、奢ってよね。行きたいって言ってた店のフルーツパフェ」
ウィンクしながらズシが言った。
ダンデが掠れ声で「あ、扱いが違う……」と呟く。まだダメージから回復しきっていないようだ。
「当たり前でしょ。私、野郎には基本厳しいんだからね」
ズシは腕を組み、ジト目でダンデを見下ろす。
「はあ……。ちゃんと迎えに来なさいよ。私の友達、泣かせないでよね」
そんなわけで、無事(とは言えないか。ダンデのお尻が犠牲になった)ズシにもダンデの帰還を知らせることができたのだった。
ちなみに、ズシはジラーチを知らなかった。私よりポケモンのゲームに詳しいズシが、だ。
ネットでヒットしたジラーチのページを見せても、あまりピンときていないようだった。
本物のジラーチの頭を撫でながら、「こんな可愛い子、私が忘れるわけないじゃん! ゲームにいなかったわよ!」と主張していたので、本当に「ゲームのジラーチ」を知らなかったんだと思う。
ダンデもジラーチを知らなかったし、何か共通点があるのかもしれない。
そういえば、ダンデも――「ゲームのダンデ」も、こっちの世界の人たちから徐々に忘れられつつあるんだよね。
……もしかして、世界を超えたら存在を忘れられたりするんだろうか。
片方(移動先)の世界に一定時間いたら、元いた世界から存在が消える、みたいな。
ダンデとジラーチの共通点ってそこしかないわけで。
まあ、こっちの世界のゲームがダンデがいた世界のポケモン全部を反映していないかもしれないけど。こういう可能性、ありそうだよね……?
「あ、そうだ。ダンデが帰るなら動画もう撮れないわね。チャンネル閉鎖しないといけないじゃない」
「あー、それもあったね」
「急で悪いけど、明日、動画撮るわよ。閉鎖のお知らせってやつ」
「分かった。ズシの家に行けばいいんだよな」
ジラーチの力が溜まるのは3日後。それまでに準備を済ませておかないとね。
「あっ。あとあんたたち、デートでも行ってきたら?」
「――え?」
「で、――?」
間抜けな声が出てしまった。
ダンデも私と同じような反応をしている。
「ズシ、何で?」
「何でって。しばらくお別れなんでしょ。せっかくだから、思い出作って来なさいよ。恋人らしいことのひとつ2つ、なくてどうするのよ」
デート、か。
私はちらりとダンデを盗み見る。
今まで2人で出掛けたことはあったけど、それはお付き合いする前の話であって。
そっか。恋人としてデートするのは、これが初めてなのか。
――同時に、最後でもあるのだけど……。
ずきん、と胸が鈍く傷んだけど、それを振り払うようにして、私はダンデに笑いかける。
「ダンデ。デート、しよっか」
「そうだな! どこに行く?」
「あー。はいはい。提案しといてなんだけど、私の前で打ち合わせすんのやめてね」
ズシが顔をしかめた。
「もう古い言葉だけど、一応言っておくわ」
「リア充爆発しろ」
***
そうして現在。
私たちは電車に乗り、浅草を目指している。ダンデが日本にいるのは今日で最後。せっかくだし、有名な観光地に連れて行きたいと思ったのが浅草を選んだ理由だった。
ちなみに、ダンデの上着のポケットにはボールに入ったリザードンがいる。デートだからって置いていかないよ。ダンデの大事な相棒だからね。
ジラーチはお留守番。力を溜めるため「眠り繭」と呼ばれる形態になって、リビングの端の方で眠っている。
「ふぁぁ……」
「眠いのか?」
「ん? んー、ちょっとね」
私は曖昧に笑った。ダンデが帰るので、とあるものを内緒で作っているのだ。仕事もあったから、寝る時間を削って昨日やっと完成させた。寝たのは2時。ちょっと眠い。
隣に座っているダンデが、心配そうに私を覗き込む。
「寝なくていいのか。着いたら起こすぜ」
「大丈夫だよ。ありがとう」
電車でも私たちは手を繋いでいる。1秒でも離れたくない。そう主張するように、ダンデがきゅっと手を握る。
小さな溜め息と共に、
「いよいよ明日か、帰るのは……。意外に時間、あったな」
と、ダンデが言った。
「そうだね。準備って言っても、ダンデの私物まとめたり引退動画撮るくらいしか、やることなかったもんね」
「なんだか実感が湧かないぜ」
「帰ったら、すぐチャンピオンカップの決勝戦なんだっけ?」
「ああ。なるべく早く再開するつもりだ。ローズ委員長の件もあるが、リーグ関係者各位に掛け合おうと思う」
それから、しばらく会ってなかったポケモンたちとの調整も必須だな、とダンデは笑う。
帰る日が決まってから、ダンデは「チャンピオンのダンデ」になることが多くなった。言動の端々に出会った当初の、「チャンピオンならそう答えるんだろうな」みたいなものを感じるのだ。
デートの今は、チャンピオンお休み中のダンデ、なんだけどね。
電車に揺られること30分。
『次は、終点。浅草、浅草です』
電車のアナウンスが目的地を告げた。
「ここで降りるんだよな」
「うん。迷子にならないように気を付けてね」
私たちは立ち上がる。
「大丈夫。キミと一緒だからな」
繋いだ手に力がこもる。
「うん。離さないでいてね」
休日ということもあって、雷門付近は人でごった返していた。
「久しぶりに来たけど、やっぱり人、多いなあ……」
国内だけじゃなくて、海外からも観光客が来てるせいだろう。私たちみたいにデートで来てる人たちもいれば、友達同士や家族連れの姿も見える。時期によっては、ここに修学旅行生が加わるはず。
「祭りでもあるのか?」
「あはは。どこもかしこも、そのくらいのにぎわいだよね」
人力車の客引きをかわし、人混みの隙間を縫い、私たちは雷門の前へ移動した。
屋根瓦がついた大きな門の真ん中には、どっしりした大きな赤い提灯が吊るされており、ど真ん中に書かれた「雷門」の文字が己の存在を主張している。浅草といえば大抵の人が思い浮かべるのは、まずこれだろう。
その左右には、提灯に負けないくらいの存在感を放つ、風神と雷神の像。近くで見るとかなりの迫力がある。この顔で怒られたら泣いてしまいそうだ。
「テレビで見たことがあるぜ。これが、雷門か」
「うん。浅草のシンボルなんだよ」
雷門は、浅草寺の総門で、正式名称は「風雷神門」というらしい。左右の風神と雷神から取っているのだろうか?
「写真撮ろっか?」
「いいな。撮ろうぜ」
私はスマホをインカメラに切り替えて、ダンデと肩を寄せ合う。
「オレがシャッター押すぜ。こういうときは男が撮った方が綺麗に撮れるらしい。手ブレしにくいとか言ってたぜ」
「誰が?」
「キバナだぜ! ファンと撮るときのコツとか自撮りのコツとか、教えてくれたんだ。こういうときに役立つとは思わなかったぜ」
「なるほど、キバナ様か」
自撮りよくしてるみたいだしね。キバナ様が言うなら間違いないでしょう。
「んー? 、もう少し寄ってくれ」
「はーい」
「もうちょっと」
ダンデに肩を優しく掴まれ、引き寄せられる。数ミリの隙間もないくらい密着してしまい、少しドキドキする。カメラで顔を確認する。……赤くなってない。よし。
「雷門も写ってるな。よし、撮るぜ」
カシャカシャとシャッター音が2回鳴る。2枚撮ってくれたのか。スマホを確認すると、いい笑顔の私とダンデが、雷門をバックにして写っていた。
「……よし、オッケー。ダンデに送ってあげる」
「ああ、頼む」
そして再び手を繋ぎ、私たちは雷門をくぐり抜ける。
「ちなみにね。この提灯の底、龍が彫ってあるんだよ。ほらこれ」
「――リュウ? これが? ドラゴンタイプか?」
「まあ……、ドラゴンタイプだよね?」
「あの姿、ホウエン地方にいるらしいレックウザに似てるんだぜ」
「え、ああいうのいるの?」
なんて会話をしながら、私たちは仲見世通りを歩いていった。